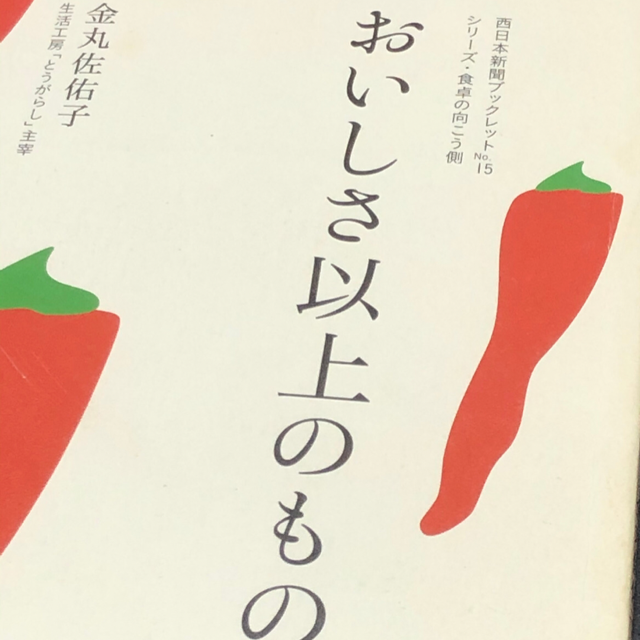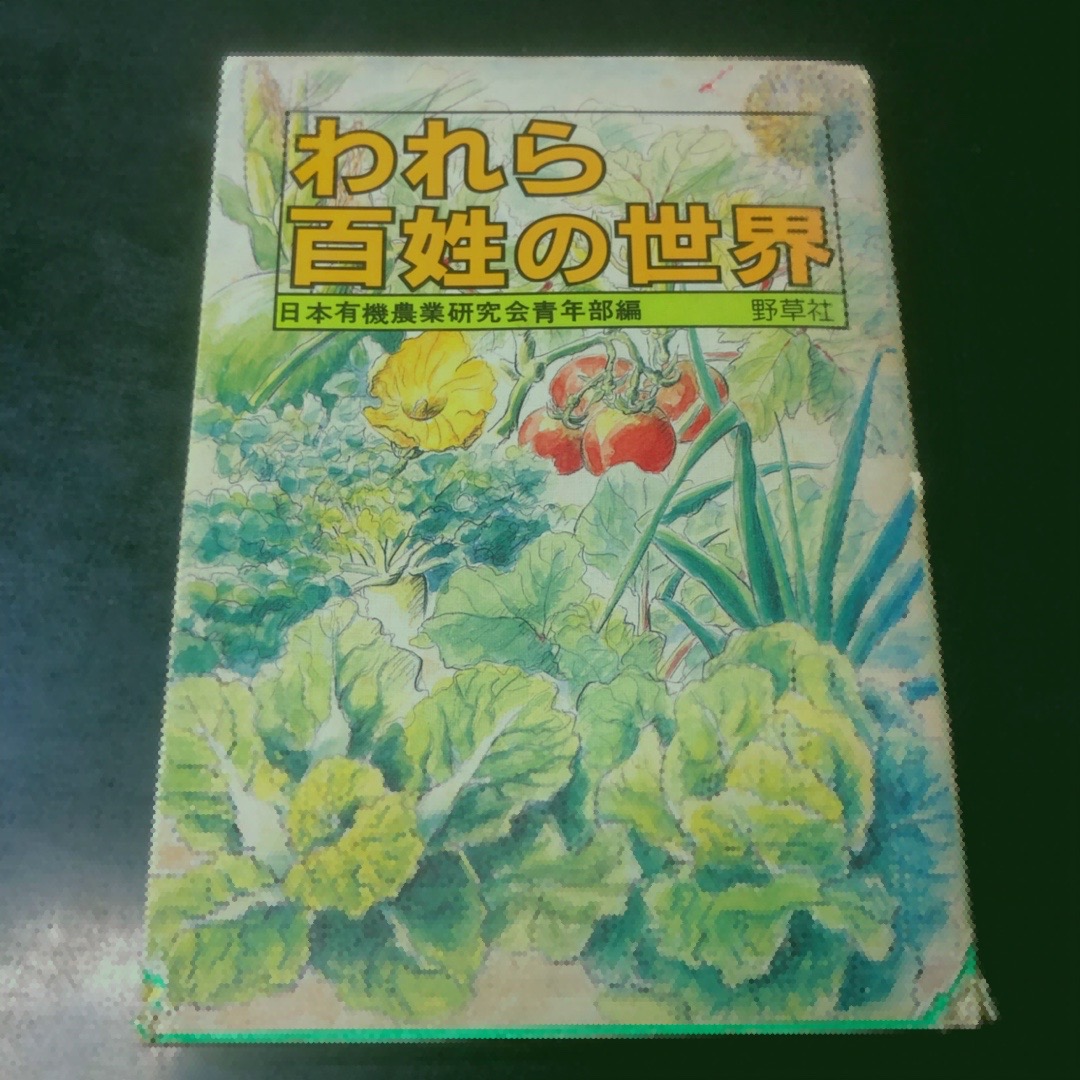7月29日30日の2日間かけて山形の生産者の小関さん、若林さん、菅原さんを訪ねてきました。今回から何回かに分けてそのご報告をいたします。今週は長井市の若林和彦(わかばやしかずひこ)さんをご紹介させていただきます。若林さんからは特別栽培ひとめぼれや大豆や黒豆、そして、若林さんの大豆で作られた味噌と納豆をいただいています。若林さんは現在69歳、高校を卒業すると同時に家業である農業を継がれました。「継いだ当時は、田んぼは山地に6反と平地に4反くらいの1町歩位しかない小さな農家でしたが、丁度その頃から、山形県の土地改良事業が本格的に始まって、それで、農地の区画整理や用水や農道の整備、農地の造成がすすめられていって、その中で、積極的に自分も農地を増やしていきました。そして、現在は25町歩の面積で営農しています。そのうち、半分は耕作転作地(減反政策により義務付けられています)で大豆や蕎麦等を作っています。米は全て特別栽培、『げんきの市場』さんに送っている大豆と黒豆に関しては無農薬です。ただ、今年は害虫が多くて、いよいよ無農薬は、難しいかもしれません。」との事でした。
全国的にカメムシの異常発生が大問題になっており、私が「やはり、カメムシですか?」とお伺いすると、「確かに多いけどそれ以外にも色々多いですよ。」との事。そして、カメムシにも有効といわれているネオニコチノイド系農薬を使うのかお伺いすると、「使いません」とキッパリと答えられました。「それ以外の農薬を使って、散布する時期やかけ方などを精査して出来る限り効果的に防除してカメムシにも対応します。」ネオニコチノイド系農薬は、自然界の生態系や人間に与える様々な影響が危惧されており、若林さんは「新農薬ネオニコチノイドが脅すミツバチ・生態系・人間」(NPO法人 ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議刊)の冊子を私に差し出し、「時代さ変わっても、自然や土、それに食や命の大切さは変わらないのです」と、その思いを話されました。
現在、若林さんはレインボープラン推進協議会の会長をされています。レインボープランの正式名称は「台所と農業をつなぐ・ながい計画」で、1988年に開催された長井市の将来を描く市民会議の中で、地域の自然と農と食をどう守るかを話し合う中で生まれました。その後、市民と行政が協力して8年後にコンポストセンター(生ごみ堆肥化センター)を稼働させ、現在5000件の市民が生ごみを分別し、行政はその収集とコンポスト化を、そして農家はコンポストを使って農産物を生産して市民へ販売するという循環型システムを構築しています。若林さんはスタート当初からレインボープランの中心人物の一人として参加されています。「なぜ市民参加型事業が続いてきたか」、その理由を尋ねると「様々な課題を乗り越えながら続いているのは、この地域の豊かさを子供の世代に渡したいという気持ちからです。それは長沼孝三さんが説かれた『長井の心』なんです」との事。長沼氏は郷土の生んだ著名な彫刻家で、「長井の豊かな自然環境が子供たちや人々の心を育み、そして、その中で『慈愛』が形作られる」というものです。現在、若林さんのご子息の敦(あつし)さん(39歳)がお父様の後を継がれています。そして、敦さんは 最上川水系の主要な支流で長井市に流れる置賜野川の生活用水が一切入らない上流から水田用水を取水して、特別栽培「野川清流米」を生産されています。若林さんの「長井の心」は、次の世代へと確かに受け継がれています。