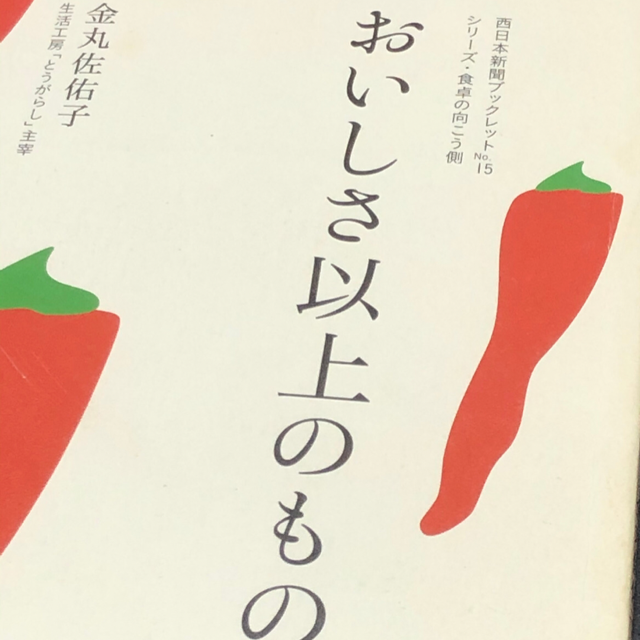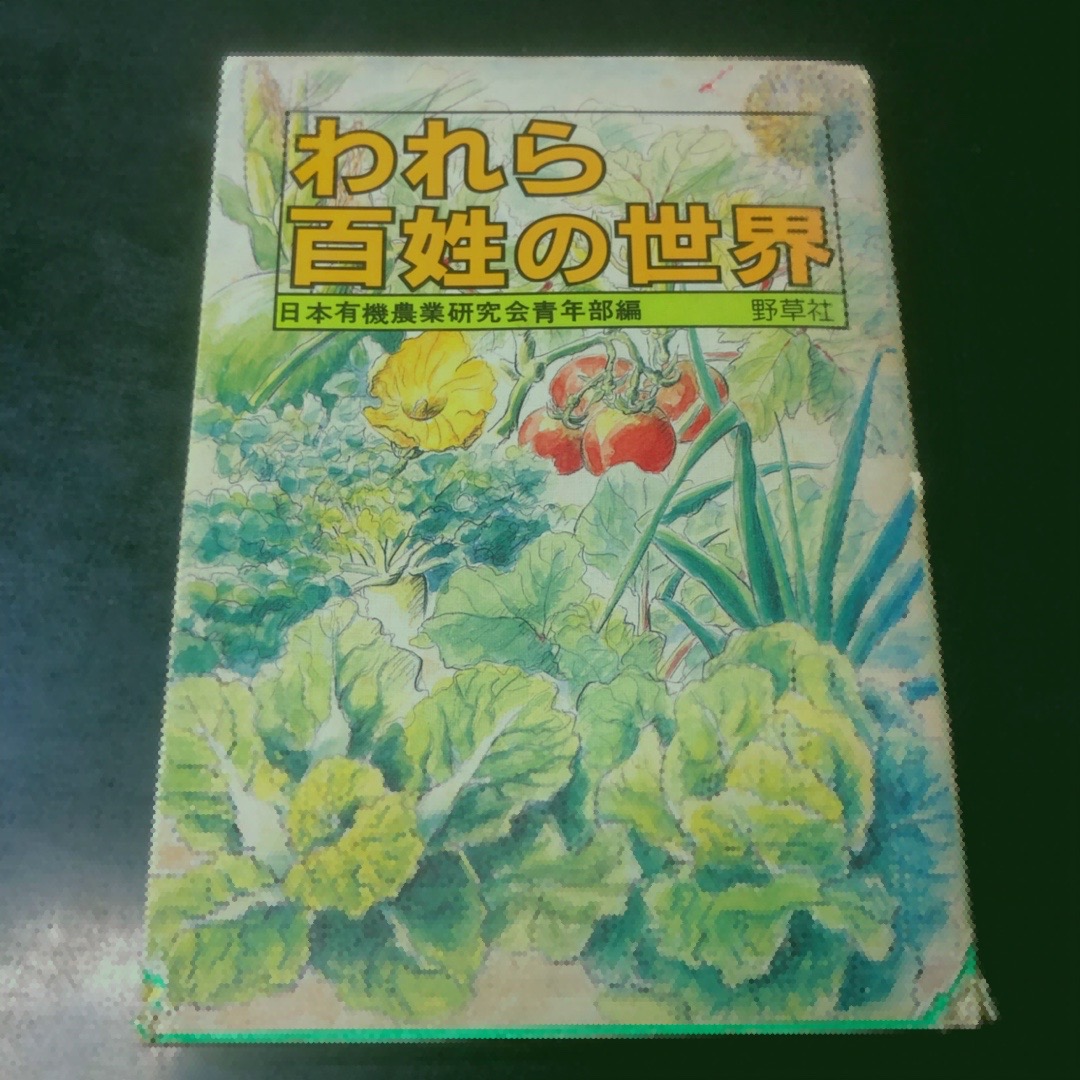2月14日、政府が備蓄米の放出を決定いたしました。初回は15万トンを放出し、2回目以降はコメの流通状況の調査を踏まえて量を決めるとしています。放出されるのは令和6年度産米を中心に5年産米も含まれ、そして売り渡した業者からは、原則、1年以内に同じ量を政府が備蓄米として買い戻すことを条件としています。農林水産省の見解ではコメの収穫量は前年より18万トン増えたのですが、JAなどの集荷業者が農家から買い集めた米の量は前年の年より21万トン少なく、今回、その21万トンと同じ量の備蓄米を放出する形になりました。3月半ばには集荷業者へ引き渡しが始まり、3月下旬以降消費者の手元に順次届くという見方がされています。今後、放出される備蓄米により価格は安定したとしても、今回の「米価の高騰」は単純な問題ではありません。
令和6年度最終的な2024年米の作況指数は101で平年並みということですが、埼玉県では97で昨年より決して良くありません。さらに生産現場の声は「お米が穫れない」という声が多く、高温やカメムシの大量発生の被害により発表された数字以上に悪いのが実感です。元農水省の官僚で農政アナリストの山下一仁(ヤマシタ カズヒト)氏は、「政府は米価高騰の背景を、外国人や転売ヤー等他の業者がため込み、本来あるはずの21万トンが流通から消えたからだと主張している。農協の集荷割合は食糧管理制度時代の95%から50%に低下しており、農協の集荷量と全体の供給量とは別だ。猛暑などで昨年40万トン不足し、本来なら昨年10月から食べる24年産米を先食いした為、24年産が18万トン増産されても22万トン足りない。消えたのではなくコメがないから、集荷競争が激化して農協の集荷量が減ったと見るべきだろう」と、指摘されています。
さらに山下氏は、この状況を生んだその背景には、戦後、日本が進めてきた減反政策といったお米の生産調整があり、「JA農協と農林水産省は、コメの需要が毎年10万トンずつ減少するという前提で減反(生産調整)=作付面積の減少を進めてきた。前年比10万トン減少という前提でコメの作付面積を減らしていれば、作況指数が前年並みの100だとしても毎年供給される米の生産量は10万トンづつ減っていく事になり、それ故、わずかなきっかけによる需要増でも『コメ不足』が起きる原因になる」と解説されています。今、このような状況の中で、食糧安保の面から考えても、コメの増産へ切り替える事が必要に思うのですが、それは決して単純な事ではありません。
減反政策が始まった1970年466万戸いた稲作農家は減少を続け2020年70万戸へと実に7割近くも減少を続けています。さらに生産量は同じ50年間で1253万トンから776万トンと4割以上減少しています(出典:農林水産省)。この原因は単純に減反政策だけによるものではなく、一言でいえばお米を作っても生計が成り立たない現実があります。農林省の営農類型別経営統計の平成30年の水田作経営(全国平均)の1経営体当たりの農業粗収益は265万円、農業経営費は209万円、農業所得は56万円という数字が並んでいます。それ故「アメリカやEUのように農家の所得保護を進めるべき」という指摘があります。ただそれでだけで問題が解決出来るとは思えません。今、私たちは生命を育む食べ物を育てる仕事に、素直に感謝し手を合わす文化を取り戻す時です。