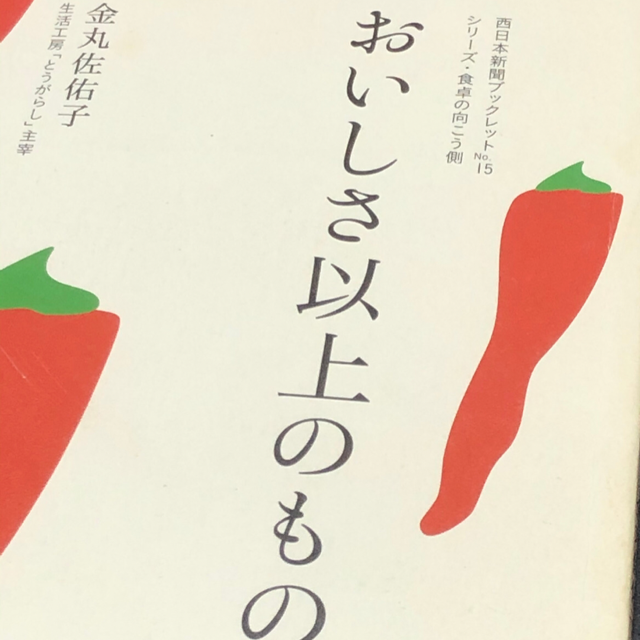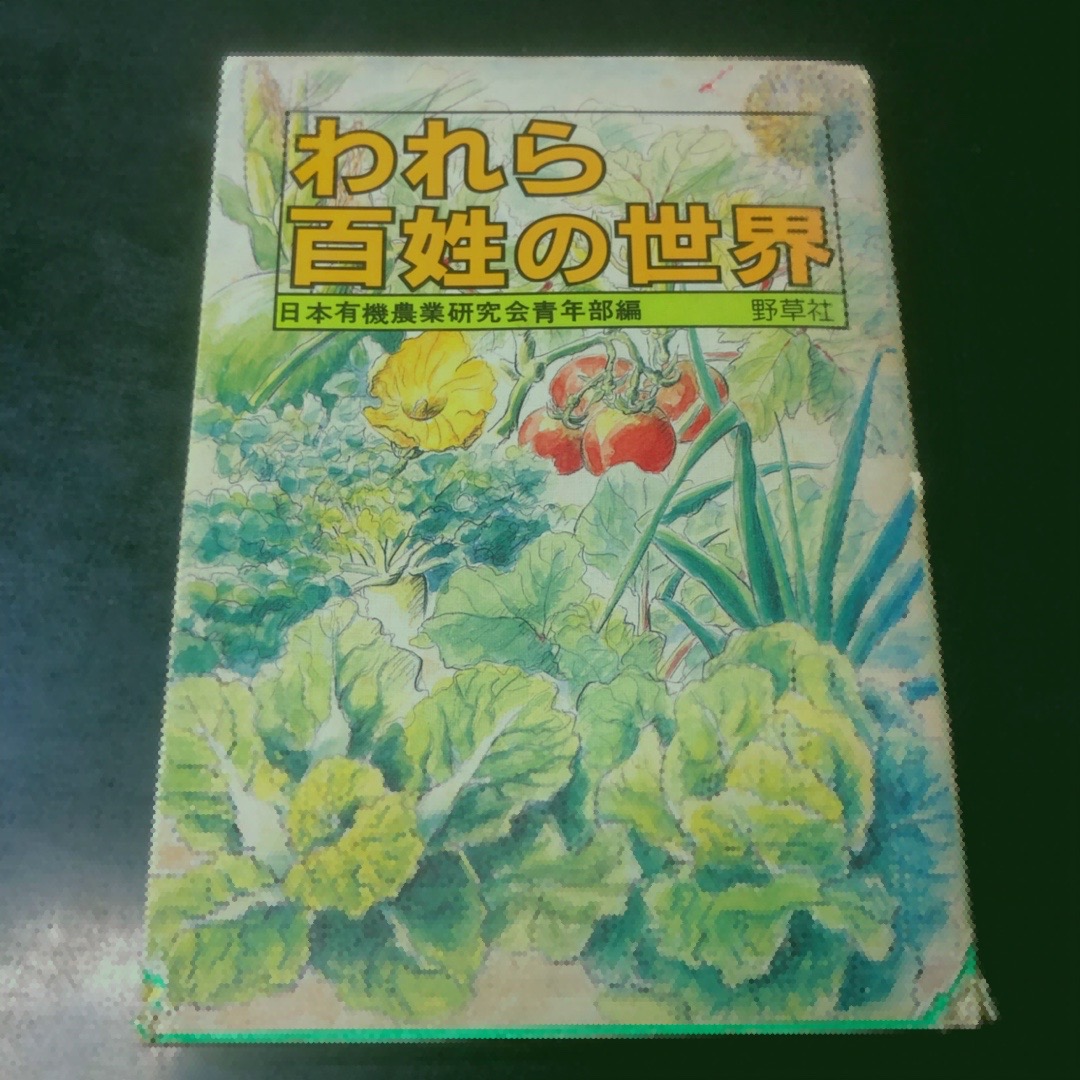この国の農業の未来 野菜情報VOL.756 令和7年7/13~7/19
昨年から続いている「令和の米騒動」の中で、政府はこれからの農業政策のあり方をめぐって、今後5年間でおよそ2兆5000億円の予算を確保し、「農家の所得向上」を目指すという方針を打ち出しました。その内訳は①農地大区画化による低コストの推進②スマート農業の技術の導入の加速化③コメの輸出目標を達成するための販路拡大の3本柱です。つまり、大規模農家を増やしドローンやAIを駆使したスマート農業で輸出力のある農業従事者を育てるというものです。今、マスメディアやSNSでは、経済性の高い?(投資が大きく汎用性の低い)この農業を大きく取り上げています。農業は命を扱う特別な営みであり、単純に経済の成長性で計るべきではなく「命の循環」を担う仕事としての役割があります。日本の農業の未来は本当にそれでいいのでしょうか?
三菱総合研究所では、日本の農業従事者の農地面積が3ha以下が全体の84%、残りの16%が3ha以上で、その16%の農家で現在の全農地面積の70%をカバーできるとしています。この今回の政府が掲げた施策を後押しする為の経済性だけを重視したこの未来像は、これからの日本の農業の大規模化を推進させていくでしょう。しかし、そうした大規模栽培は農薬・化学肥料の使用増加、大量な水の消費、大型機械による土壌の影響や、生物多様性等の自然を破棄する工業化農業であり、環境負荷となります。そして、農村人口の減少を招き、農村自体が維持できなくなり、それは農村の消滅へとなり、そして日本の国土と共にその根底にある文化をも荒廃へと導いていきます。
国連は2014年に小規模家族農業推進とアグロエコロジー推進(生態系を守る)にかじ取りをしました。農薬・化学肥料を使用した大規模市場中心農業から、資源やエネルギーの使用を抑え、生態系を守る循環型農業への変化でした。単位面積から得られる栄養(多品種・ミネラル・常在菌)という面でも小規模農業が有利です。世界では1999年から2019年の20年間で有機農業に携わる人が15倍以上に増えています。特に増えたのはインド、タイ等のアジアの国やアフリカやラテンアメリカの国々です。こうした地域では農家が地域でグループを作り有機農業への転換を進め、そして、その農業が地域経済を活発にさせる役割を担っています。そうした国々では貧困層の人たちが「飢えを無くす為にアグロエコロジーを!」という未来を変えるスローガンを掲げています。
日本の食糧自給率はカロリーベースで38%(種苗や繁殖の部分を考えると本当はもっと低いです)で先進国の中で最低です。アメリカのシンクタンクが、もし核戦争などにより貿易が途絶えてしまうと2年以内に世界中で少なくとも7000万の餓死者がでて、そのうちの約3割が日本人で、国民の3人の1人が餓死するという予測を発表しています。文字どおり食料は社会の基盤であり、特別の地位にあるべきものです。この問題に対して、どのような手を打つか、今後の日本の大きなカギになります。7月7日のNHKニュースでは、6月23日から28日の一週間のスーパーでのコメ販売価格は5kg当たり3672円で、前の週より129円値下がりしました。値下がりは6週連続で随意契約の備蓄米の市場流通が進んだ為のようです。そうした中で、米価格が落ち着けば、「令和の米騒動」も、私たちの国が抱えている農業問題も、やがて忘れ去られていくのでしょうか?
参考文献「オンライン学習会:米騒動とバイオテクノロジーその2」OKシードプロジェクト