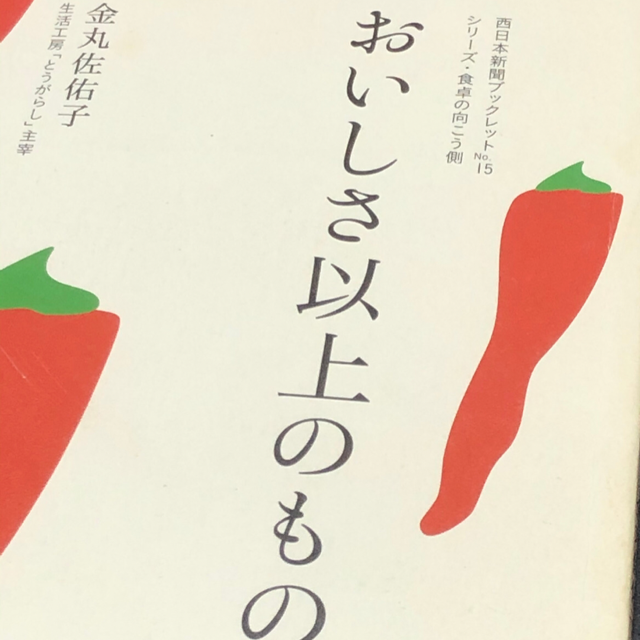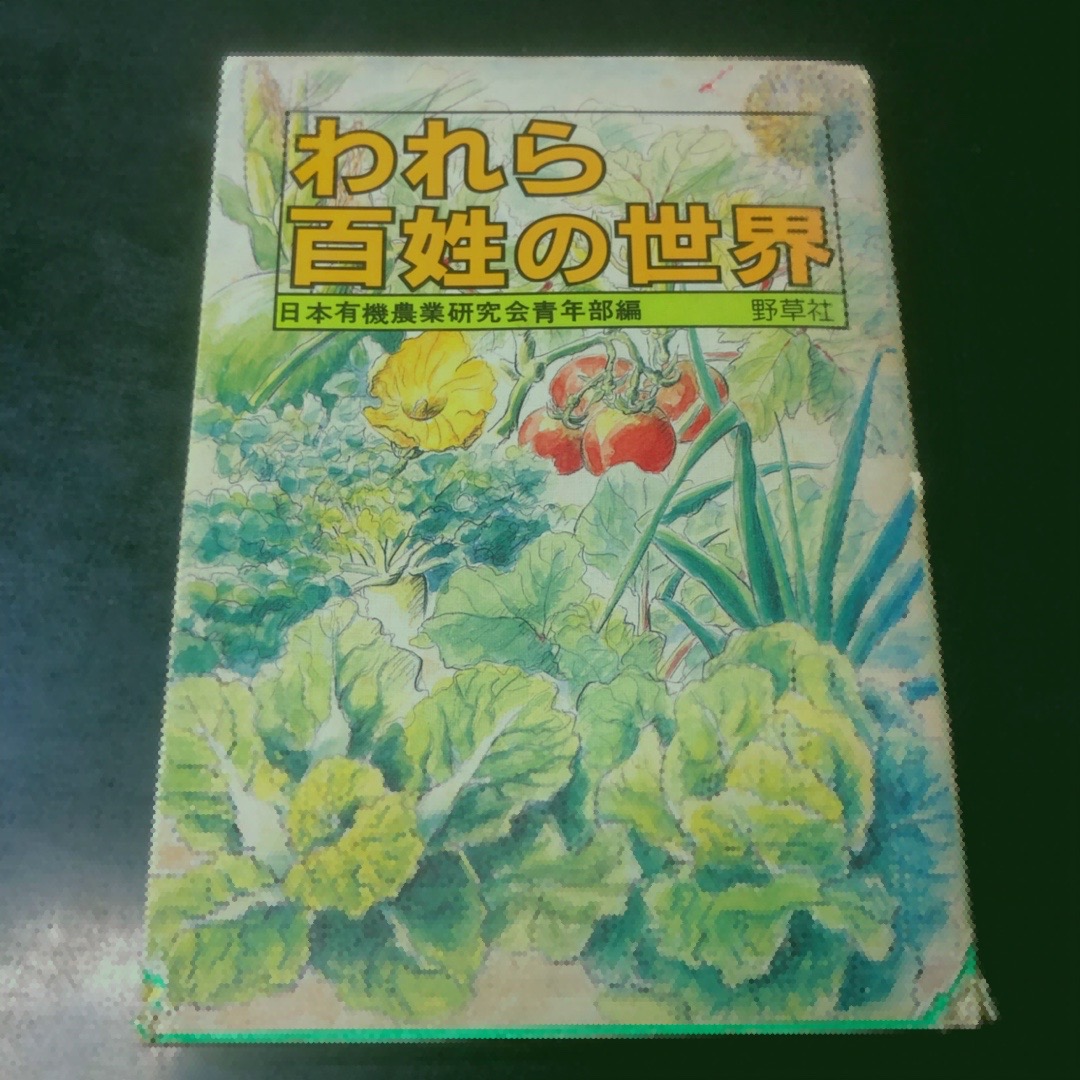野菜情報VOL.765令和7年10/12~10/18
先週の野菜情報VOL.767「東日本大震災を経て私たちがたどり着いた切実なる思い」で書かせていただいた通り、私たち「げんきの市場」は、自身の健康と共に広がる地球の健康を暮らしの中で育てていきたいと願っています。そして、それこそが私たちが次の時代の価値として創造したい、「生命という価値を中心にした経済」だからです。その為に私たちが取り組んでいる1つが生産者と消費者、そして流通の「げんきの市場」の三者がトライアングルで繋がる「間接提携」です。
1970年代初頭から、有機農業で育てた農産物を生産者(有機農家)が直接食べる人(消費者)に届ける「提携」が日本各地でスタートし、やがて全国各地で多様な提携団体が生まれていきました。私がいた「あいのう野菜の会」もそうした団体の一つで、愛農生産者と都会の消費者を結ぶ事務局として働いていました。「提携」は「食の安全」を望む消費者により始まりましたが、同時に「農」と「食」が直接つながる事により、「商品」としての作物から「命を育む食べ物」への転換があり、それは私たちと「自然」との繋がりを本来の姿に戻す力があると信じて活動していました。
しかし、実際に「事務局」として働いている中で「消費者」と「生産者」が直接つながる事により発生するマイナスが次第に大きく見えるようになりました。例えば野菜の品質へのクレームの問題です。当時の有機農業が発展途上の時代であるという事もありましたが、本来、農薬や化学肥料は自然界の中で作物の生産を安定させる目的の為に使われます。それを使わないという事は野菜の見栄えや虫食い、腐りや劣化などが起きるリスクが上がり、一般的な作物と比べて規格性も併せて「商品性」は低くなる事が多々ありました。ほとんどの消費者の方がそれを承知の上で、それよりも「安全性」が大事という事で会に参加されていましたが、それでも「食べられないのにお金は払えない。でも、生産者の努力はわかるからクレームも言いづらい…。それが重なると…。」といった声も頂きました。また、生産者からも「生産量を増やしたくても会員が増えないと畑で腐らしてしまう…。」といった声も頂戴する事がありました。そうした中で、「本当に食べる人にとって良いものであるならば、普通に1人でも多くの人に手渡し、そして、その野菜を手にした人たちがいつかその価値に気づいてもらえればそれでいい。」と考え、「げんきの市場」をスタート致しました。
ただそのような思いでスタートはしましたが、それでも「提携」がもつ「食の安全」だけではなく、「私たちと地球とのボタンをかけ違いを直す力」を野菜の中に持ち続づけたいと願っていました。クレーム処理等のリスクをカバーしながら、「提携」が持っていた未来への希望の力を繋げていければと考えています。1970年初めにスタートしたコンビニやその時代に広まったドラッグストアはこの50年の中で拡大の一途をたどりましたが、同じ時代にスタートした有機農業の「提携」はそうはなる事が出来ませんでした。老子は「道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生じる。」と「道徳経」の中で説いています。「消費者」と「生産者」と「流通」が「間接提携」というトライアングルになる事で、これからの時代の中で市民権を得て、広く流れる事を願います。そしてこの「間接提携」を通し「生命価値経済」が広がる未来に、是非力をお貸しください。