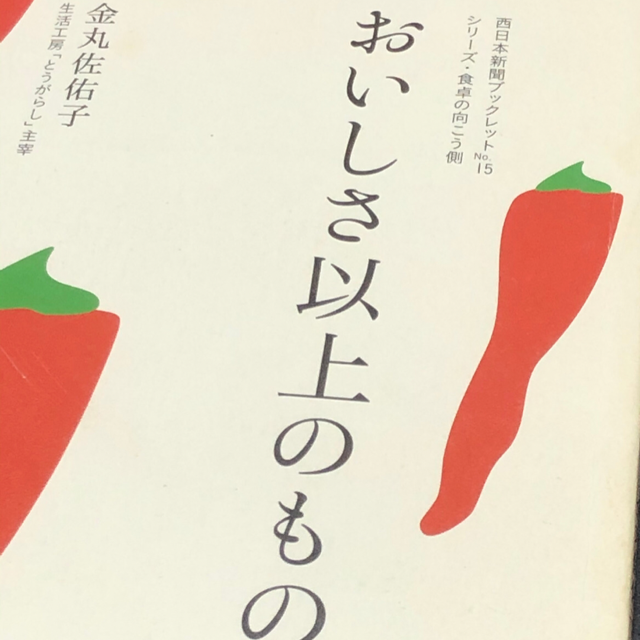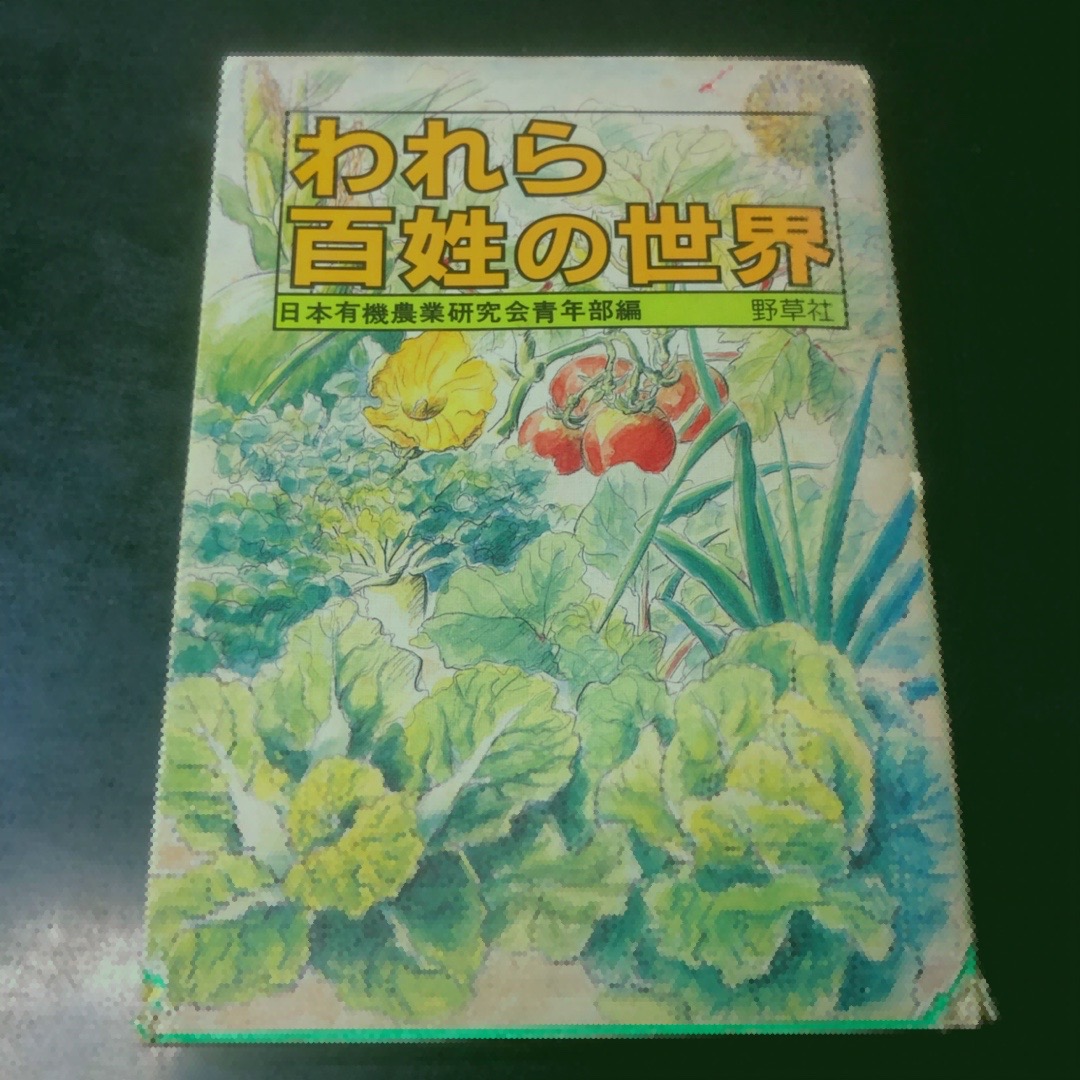1月15日、今年も山形県の菅原義弘さんが「げんきの市場」を訪ねてくださいました。菅原さんはJAS有機栽培「雪若丸」の米生産者です。最初に頂いたのが令和3年、菅原さんが26歳の時でした。それから4年が過ぎ菅原さんはまもなく30歳を迎えようとしています。始めてお会いした時、農業への思いを語りながらも、「他の世界で働く同世代の人たちとの交流が増えるにつけ、あまりに違う労働環境にやはり色々と悩むこともあります」と、ご自身の状況を率直に語られていました。しかし、結婚をされ、その後、お子様も産れ、菅原さんの思いや取り巻く環境など様々な事が変わっていきました。
「まず、最初に変わったのが親父ですね。米作りを始めた1年目は色々と栽培について口出しをしてきましたが、2年目になると私に対して何も言わなくなり、今では栽培技術について私に聞いてくるようになりました。山形には『農村通信』という稲作栽培技術向上を取り組んできた地域紙があって(2020年廃刊)、そこが若手育成を目的にした『稲株塾』(とうしゅじゅく)を主宰していています。そこに私も参加させていただき、稲の成長や生態に合わせて必要に応じて作業をし、肥料を入れる方法を学びました。今までの農業は10人10色のやり方で、とにかく丁寧さが命でしたが、いかに効率よく作業するかという、そうした最新の技術を学べた事が自信になっています。また、自分の村は対馬(つしま)という集落で、そこの会計を担当するようになり、今までは話すことがなかった人たちと会う機会が増え、集落の人たちの事もよく知るようになりました。対馬全体で50haの田んぼがあり、現在20世帯が稲作をしています。その中で専業農家は私を含めて3世帯だけで、その20世帯の中でも高齢化が進んでいて、耕作放棄地をつくらないために他の人の田んぼを受け入れる事が出来るのは、集落の中で自分一人しかいません。その為、今年は12haだった農地を3~4年後には20 haまで増やし、最終的には25haまで増やしていく予定です。そうした状況の中で、有機栽培を減らし、特別栽培に切り替えていこうかと考えています。有機栽培は除草だけでも、カモ、手取り除草、機械除草の3回必要で、広い面積でやるにはあまりにも手間がかかり過ぎます。面積を広げていく為には有機栽培では物理的に難しいです。5年前よりも有機のお米を作っている人は25%も減っている現状もそう言った事が影響していると思いますね」。
菅原さんの農業は農業大国山形の米作りを守り育てて行く、そうした未来に大きく関わっています。そして、それは日本の未来を守る食糧安保の問題とも大きく関係しているのです。その菅原さんの考えに対して、私は「今まで通り、有機栽培の雪若丸をつくり続けてください」とお願いしましたが、同時に「もちろん特別栽培の雪若丸でも売り続けます。」と、約束しました。今年中には2人目のお子様が産れる予定の菅原さんには、もはや農業を続けていく事への迷いはありません。「げんきの市場」は菅原さんが歩む道のりをこれからも心より応援をしたいと考えております。